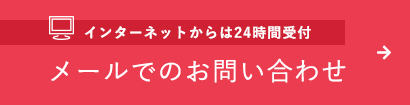地方の別荘地に対する交換詐欺や測量詐欺にご注意を!

昭和後期からバブルの頃に購入した別荘地が、詐欺のターゲットにされています。
当協会で理事長を務めています加瀨義明です。
昭和の後半から平成初頭にかけて、いずれ高く売れるんじゃないかと思って、別荘を建てる予定もないのに地方の別荘地を買われていた方が結構身近にいらっしゃったりするので、全国的には相当な人数の方々が別荘地を買ってそのまま放置しているのではないでしょうか。
そして、相続登記が義務化されたことで、誰も相続したがらない使わない土地を自分の代で手放せたらいいなと考えている方も多くなっています。
そこで現在どのような金額でご自身が所有されている周辺の土地が売買されているのかを調べれば、目を疑うような安値で販売されている現実を知ることになるでしょう。
そのような金額でもなかなか買い手がつかないのが実際のところです。
しかし、過去に数百万円を支払って買った土地をただ同然で譲渡したり、こちらで更にお金を支出して処分するなんていうことには抵抗があると考えていらっしゃる方が多いのが現実です。
そのような方々をターゲットに詐欺師たちは魔の手を伸ばしてきます。
詐欺師たち(宅建業の免許を持った不動産業者であったりするが、実際は休眠会社を買い取ったりしてまともな不動産業者になりすましている)は、昔の別荘分譲地の土地所有者を法務局の登記情報から調べて皆さんの連絡先を把握して近づいてきます。
では、どのような手口の詐欺が多いのか、事例を2つご紹介いたします。
隣地との境界を復元すれば売れると言ってくる詐欺

所有者が物件の近くに住んでいないことがほとんどなのをいいことに、現地なんてずっと確認していないであろうような荒れた土地の所有者さんに連絡してきて、
「お宅の所有物件の近くで売却物件を取り扱っていて、そこそこ反響があるので、お宅の土地も隣地との境界を確認できるようにすれば売却できる」
といって、調査費用とか測量費用だと言って30万円くらいを所有者に先に払わせて、結果何もしてくれないでそのまま音信不通になってしまうパターン。
普通に売れないような土地をいかにも整地すれば売れると思い込ませて費用を騙し取ろうとします。
しかし地元ではなく遠く離れた他県の業者だったり(ホームページでは別荘地をたくさん扱っているように見せかけている)するので、現地近くで古くから実際に営業しているような不動産業者に周辺物件の動きを確認してみたり、所有者様が信頼のおける不動産業者に間に入ってもらって対応してもらう等の防御策が必要です。
交換差金を騙し取る詐欺

交換詐欺を働きかけてくる詐欺業者は、
「お宅様で〇〇件〇〇市内に別荘地をお持ちですよね?
実はお宅様の物件の近くの土地を売買していて、買いたいと名乗りを上げてくるお客様が多くて、近隣の土地所有者様が売却を希望でしたら弊社のお客様をご紹介しようと思ってご連絡させていただきました。
何なら、弊社で所有して売却に出した土地の買主が決まって近々に契約予定なので、弊社の土地とお宅様の土地の売買価格の差額をもらえれば、弊社の土地とお宅様の土地を先に交換しても良いですよ。
弊社の土地は200万円で買主が決まっていて、お宅様の土地は時間かければ100万円なら売れる自信があるので、弊社の土地とお宅様の土地の価値の差額の100万円を支払ってもらえれば、弊社の土地をお宅様名義にして今決まっている買主と契約すれば、200万円の売買代金がもらえるから、実質100万円で本来の自分の土地を売ったのと同じになりますよ。
弊社はお宅様から引き取った土地を他のお客様に100万円で売れば、実質200万円で土地を売ったのと同じになるから大丈夫です。」
と言って不動産の交換と差額の代金の支払いを持ちかけてきます。
交換の契約はお客様の自宅にその詐欺業者が来て、相対で行いその場で交換差金の支払いをさせて、司法書士も通さずにお客様の権利証と印鑑証明書と委任状を預かって行ってしまいます。
後日、その業者は買主との契約を取り持ってくれることなく、電話しても電話がつながらなく音信不通になってしまい、自分の土地はその詐欺業者に取られ(もしくはそのまま名義も変更されずに放置される)、交換差金も騙し取られ、見たこともない知らない土地の所有者となってしまいます(名義はちゃんと登記されますが、権利証は送られてこないことがほとんど)。
これらの事案は、不動産業者が加入している保証協会に問い合わせても、対象地が現況は「原野」もしくは「山林」であったり、ライフラインの状況も整備されていなく、すぐに建物が建てられる「宅地」ではなければ、「宅地建物」には該当しないため保証の対象とならないとされてしまうので、泣き寝入りになってしまうことがほとんどです。
ですから、知らない業者からうまい話が来たときは、必ず信頼のおける不動産業者に相談して間に入って対応してもらうことが大切です。
当協会の相談会の相談員を務めている会員は、そのようなことに精通しておりますので、不審な業者からうまい話を持ち掛けられたら、当協会にご相談のご連絡をください。
|
|
執筆者:加瀨 義明 |
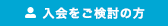
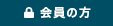
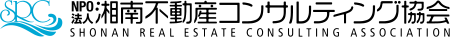




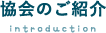







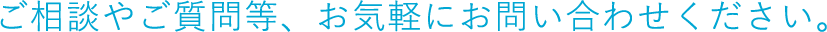
![お電話でのお問い合わせ 0466-25-5253 営業時間 10:00-17:00 [水・日曜定休]](/images/common/contact_tel.png?t=2)