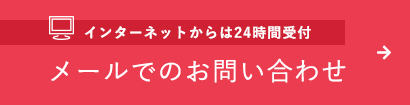農地を所有していたら・受け継いでしまったら。

当協会のホームページをご覧頂きありがとうございます。
当協会では常務理事・財務担当をさせて頂いております吉原と申します。
不動産コンサルティングというと、一般的には「不動産の有効活用」、「資産運用」、「相続対策」などが思い浮かびますが、それらとはちょっと違った内容になりますがご一読頂けましたら幸いと存じます。
今回、テーマとして取り上げさせて頂くのは「農地」です。農地も不動産であり、資産ではあります。
当然ながら、農家であれば必須の資産ですから大切なものには違いないのですが、都市近郊の農家の場合ですと、子供たち(後継者)が就農せず、一般企業に就職または公務員になられているといったケースも多いと思います。
そういった場合、休日に多少、農業のお手伝いをすることはありますが、本格的に農家に転職するという可能性は、ほぼ無いのではないかと思います。
特に問題が生じない限り、現状維持の状態が続くのですが、こと農地に関しては、農地法という法律で、かなり厳しい制限がかかっていますので、そのことを知らずにいると、なにか事が起きたときに苦労する羽目になりますので、農地に対する知識を知っておいて損はないと思います。
市街化区域と市街化調整区域では天と地の差
土地をなにかしようとするとき(売買や宅地造成など)、その対象地の面積や区域によって、都市計画法や宅地造成及び特定盛土規制法などの法律により各種許可等が必要となる場合もありますが、そういった制限に抵触しない場合は、宅地であれ雑種地であれ山林であれ、基本的に許可は要りません。
ところが、農地に関しては、現況がどのような状態であったとしても、登記地目が農地のときは許可もしくは届出が必要となります。
対象地が市街化区域の場合は、それほど気にすることはありません。市街化区域でかつて畑であった土地に貸家を建てて貸していたが、地目を宅地に変更せず、登記地目が畑のままであった、なんていうことはしばしば見受けられます。
その場合は権利の設定・移転がなければ4条の届出、あれば5条の届出を各市町村の農業委員会に提出すれば、1週間程度で転用届が交付されますので、現況にあわせた地目に変更することができます。(依頼先によって申請費用や登記費用がかかることはありますが。)
対象地が市街化調整区域の場合は、農業委員会の許可が必要となります。許可になりますので、先の市街化区域の届出とは時間も労力も比になりません。ちなみに、農地を農地のまま取引する場合は3条の許可、農地を農地以外に転用する場合は4条の許可、農地の転用に権利の設定・移転が伴う場合は5条の許可が必要となります。
市街化調整区域の転用許可は大変
先ほど、市街化調整区域の農地転用は許可が必要と言いましたが、必ずしも許可が取れるわけではないのが農地法の厳しいところです。
各市町村の都市計画図などで色塗りされていない区域にある農地が対象の話ですが、色塗りされていないので、「農地は農地」ですよね、と全ての農地が同条件であり、特に差異は無いと思ってしまいますが、色分けされていなくても農地にも種類があります。
農用地区域内農地(市町村において農業振興地域整備計画で指定された区域)の農地は、その名の通り、農業を振興する目的地になりますので、農地として売買は可能ですが、転用は出来ません。
そういった純粋に農用地である区域から市街化区域に近づくにつれ、原則的に第1種、第2種、第3種と農地の種類が区分されています。
これらの農地も、農地を農地として売買することは出来ますが、農地転用については、第1種は不可、第2種は可能性ゼロではないがかなり大変、第3種は内容によって転用可能となります。(他に甲種農地というものもあります。)
しかしながら、所有している農地が第3種農地だったので、耕作をやめて資材置場にでも転用して貸せば良いか、と考えたとしても、そう簡単には行かないものです。
まず、その転用する対象地(農地)でなければならない必要性、転用する面積の必要性、利用に際し何をどれだけ、どのように利用するのか、といった内容的にかなりの具体性が必要となります。駐車場であれば、必要台数と駐車車両の車検証のコピー等必要になりますし、配置図等の利用計画図等も要りますので図面作成の技術も必要です。ですので、転用しておけば中古車屋にでも貸せるだろうというような、とりあえず転用、では許可はとれないでしょう。
また、市町村によって制限の差はあるかもしれませんが、対象地の前面道路にインフラが2つ以上必要という制限がある場合もあります。インフラは上水道、下水道、ガス管(電気は含まれない)となりますが、そのうち2つ以上ということになると、ガス管がある可能性は低いので、上下水道管が通っていないと転用不可となります。
たまたま、対象地の前面道路にだけ下水管が敷設されていなかったりすると、隣地は転用できたけど、こちらの農地は不可ということも有りえるということです。
転用できない農地は非農地も認められない
長年、駐車場若しくは資材置場として貸していた土地が実は農地であった(登記地目が農地)というケースも見かけることが有ります。数年前までは、もう十数年以上も前から農地じゃないから、というケースで農業委員会に相談すると、非農地で処理するしかないですね、ということで非農地証明を取得し、地目変更するということが有りました。
過去に農地転用の許可を受けていれば許可証を紛失していても、農業委員会から許可済みの証明等を発行してもらえば大丈夫ですが、許可の履歴が無い場合にこの非農地で処理する、というか、せざるを得ないというものでした。
現在では、先ほどのとおり、農地転用も厳しいのですが、この農地転用が出来ない区域の農地で、この非農地に該当するような場合、これは農地法の転用違反以外のなにものでもないという扱いに変わっています。
農業委員会に指摘されると、その結果、是正するように言われてしまいます。是正ということは、借主がいた場合は立退きしてもらい、且つ農地に戻す、ということなので、費用や時間もかかりますが、他にどうにもしようが無いのが現実です。
何もしなければ農業委員会からそのような指摘をいきなりされることは、あまりありません。(誰かから農地法違反の情報を農業委員会に報告されたりしない限りですが。)
しかしながら、農地の許可にかかわる取引等をしようとするときは、農業委員会に事前相談等を行うのですが、その際に所有者又は売主・買主の所有する農地を全て調べられてしまいますので、所有地に農地がある場合には思いもよらない場所の是正の指示を受けることもありますので注意しなければなりません。
実際のおはなし
近ごろ、実際にあった事例です。農地の一部の売却の話が出て、農業委員会へ相談にかけたところ、所有者の関係者全員が山林と思っていた土地が、実は農地であることがはじめて分かりました。確認したところ登記地目は確かに畑でしたが、戦前から畑であったことはないという主張も認められず、かつ、非農地は認められない区域の農地に該当していましたので、是正を求められました。
山林かと思っていたため、過去に賃借人が作業用の小屋(違法建築)を建てていました。建物は農業用倉庫という扱いでなんとか除去せずに済みましたが、その時に小屋を借りていた賃借人には立退料を払って立ち退いてもらうことになりました。
農地は農業資格のある人にしか買えませんが、相続では資格に関係なく相続することは出来ますので、これから相続で農地を取得する可能性がある場合、耕作する場合以外の点では農地の扱いは結構大変ですよ、ということを頭に入れておいて頂ければと思います。
当協会では、不動産や相続に関連する権利関係のほか、農地などの相談にも応じておりますので、お気軽にご相談ください。
|
|
執筆者:吉原 啓資 |
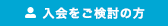
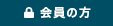
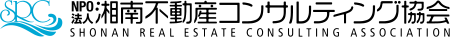




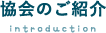







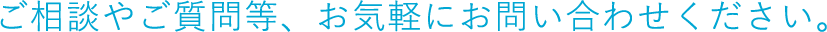
![お電話でのお問い合わせ 0466-25-5253 営業時間 10:00-17:00 [水・日曜定休]](/images/common/contact_tel.png?t=2)