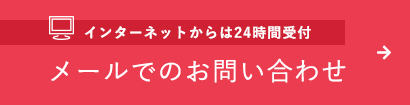共有状態はトラブルの原因になりやすい!

当協会ホームページをご覧いただきありがとうございます。
常務理事を務めております能勢です。
宅建士や不動産コンサルティングマスターの他に、行政書士の資格も取得して、相続関連や権利調整のご相談を多く承っております。
その中で、トラブルになりやすい事案が「共有」にまつわる問題です。
トラブルに発展する前に解決した案件を一つご紹介したいと思います。
当初は深く考えずに共有にしてしまいがち
この案件の登場人物は、相談者である父親のAさん、Aさんの娘Bさん、娘Bさんの夫Cさんとなります。
娘夫婦が自宅を購入する際に、Aさんは土地代金の一部として1,000万円を出資して、土地の名義をCさんが5分の3、Aさんが5分の2として登記しました。
建物はCさんが金融機関から借入をしてCさん名義となり、Aさんが担保提供者兼連帯保証人となりました。身内なので、当時は1,000万円という大金にもかかわらず、借用書も作成せず、毎月の返済計画や実際の返済も無く、単純に持分登記をするという曖昧な出資でした。
それから約20年が経過し、Aさんも80歳を超え今後の事について整理したいと考え始めました。
共有状態のリスク
このまま、何もしないで時が過ぎるとどのようなリスクが考えられるでしょうか。
まずは、Aさんが高齢のため、万が一、認知症など意思決定が難しくなった場合、ご自身でこの持分所有権を移転する事が出来なくなり、もし、娘さん家族が自宅の土地建物を売却したいとなった場合、Aさんに後見人などの代理人を選任する必要が出てきます。
次に、万が一Aさんに相続が発生した場合、娘Bさんの他にも相続人がいましたので、相続財産の分配について不公平感などが生じ対立してトラブルになる可能性があります。
また、Aさんは高齢ですので可能性は低いですが、何かしらの事情で経済状況が悪化して持分が競売にかけられた場合、第三者が共有者になり、資産価値が下がる恐れがあります。
贈与か売買か
相談者を含め関係者に集まっていただき、皆様の意見をお伺いする話し合いの場を設け、共有状態のリスクを一通りご説明させていただきました。そのうえで、総意として父Aさんとの共有を解消していく方向になりましたので、大きく分けて2つの選択肢をご提案させていただきました。
一つ目は、娘Bに贈与する方法、ニつ目は娘の夫Cに売却する方法です。実際にどのような違いがあるのでしょう。
まず、贈与した場合、娘家族の資金負担は無いものの、原則的には贈与税が課税されます。基礎控除内で持分を数年に分けて贈与していく方法や相続時精算課税制度を利用して非課税で贈与していく方法もご説明しました。
二つ目は、娘の夫Cと売買契約を締結し売却する方法です。
どのような違いが出てくるか、当協会の税理士さんに税金面、司法書士さんに登記料等の比較試算してもらいました。
その結果を踏まえてどの方向で進めていくかを検討してもらった結果、夫Cに売却する事になりました。父親であるAさんにしてみますと、持分であっても自分の財産ですので、娘の夫Cに所有権を渡すより娘Bに渡したい気持ちは強くお持ちでした。ただ、その場合であっても本当の共有状態の解消には繋がらない事を理解したようです。
今は仲が良い夫婦でも、将来の事はわかりません。結局共有状態であれば、またそこでトラブルになる可能性を秘めているわけです。
売買価格について
試算の結果を踏まえて家族会議を繰り返し、夫Cに売却する事になったわけですが、
不動産には一物四価とも五価とも言われる価格があります。四価とは、「実勢価格」・「公示価格」・「相続税評価額(路線価)」・「固定資産税評価額」の4つの価格のことを言います。
実勢価格は主に不動産の市況で、公示価格は国土交通省が、相続税評価額は国税庁が、固定資産税評価額は自治体がというように、それぞれ不動産に価値をつける主体が異なることから、このようにさまざまな価格が存在しています。
今回のような持分売買の場合、この価格に今までの経緯やお互いの感情の部分を加味して算出する必要が出てきます。
そこで、各価格を算出しご提案したうえで、お互いが納得する価格に落とし込みました。
最終的にその納得した形で売買契約が成立して無事に父Aの持分5分の2を夫Cに移転して、土地建物ともCが所有権の全部を持つ形になり、金融機関に対しての連帯保証人は解除となり全てが丸く収まりました。
当協会では、不動産や相続に関連する権利関係の調整など、杓子定規に片付けられない相談にも応じておりますので、お気軽にご相談ください。
|
|
執筆者:能勢 健一 |
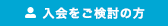
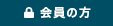
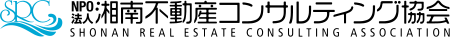




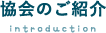







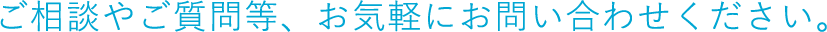
![お電話でのお問い合わせ 0466-25-5253 営業時間 10:00-17:00 [水・日曜定休]](/images/common/contact_tel.png?t=2)