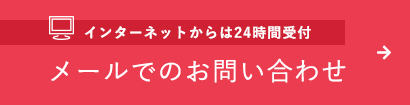相続や共有物件などの紛争案件における私的入札提案【入札合意書の例】
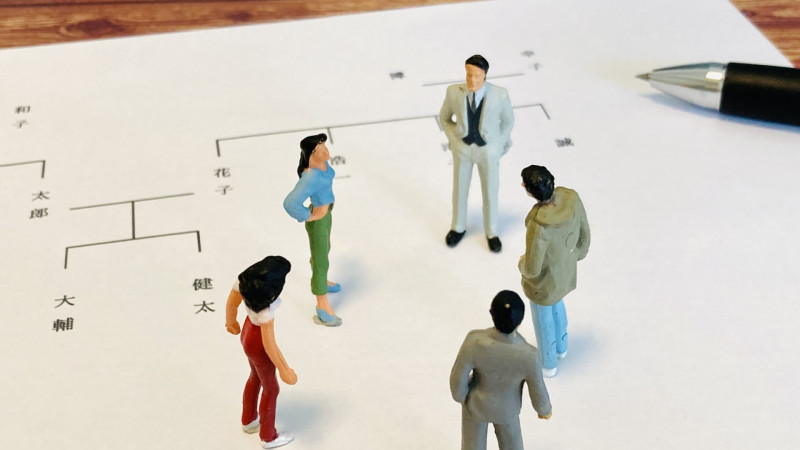
当協会理事の弁護士の鈴木洋平です。弁護士をしていますと、不動産にまつわる権利関係の争いを多数取り扱うことになります。
しかしながら、例えば、相続や離婚や債務整理が得意であるとうたっている弁護士でも、不動産の案件が得意かどうかは別の問題になります。同じ相続案件でも、遺産に不動産がある事案とない事案では必要な知識・経験・人脈など全く異なります。
わたしは、不動産にまつわる権利関係の争いを含む案件の場合には、極力その分野や地域に即した不動産業者と連携して対応することにしています。
このテーマを書籍化したものが「不動産業者のための 弁護士との協業のすすめ」(幻冬舎メディアコンサルティング)になります。今回は、この書籍のなかから、わたしが不動産業者と連携して対応した案件(相続や共有物件などの紛争案件における私的入札提案【入札合意書の例】)を一つご紹介したいと思います。
不動産の分割協議が進んでいなかった
この事案の登場人物は、独身で子がないまま死亡したAさん、兄Bさん、姉Cさん、妹Dさんとなります。Aさんの遺産は,都内のマンション,郊外の戸建など不動産で,預貯金は少なく,その他カードローンの負債で約300万円がありました(なお,住宅ローンは団信でゼロとなりました)。
この事案で紛争になった原因は、不動産の分割方法について見解が一致せず、分割協議が一向に進まないまま1年が経過していたというものです。
具体的には、Bさんがある大手の不動産業者に媒介を依頼したいと言っても、Cさんは知り合いの小さな不動産業者に媒介を依頼したいと言い、Dさんは特に無反応で何も動かない、といった具合です。
入札方式による不動産売却を提案
このため、Bさんは家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てたのですが、わたしはDさんの代理人としてこの調停に参加することになりました。そこで、わたしは、入札方式による不動産売却を提案しました。
つまり、B、C、Dさんが,各自で不動産業者に依頼して最も良い条件の買主に売却する方式です。もちろん、B、C、Dさん自身が買主として入札することも可能としました。
ここまでは不動産業者の方であっても、行ったことがある方もいらっしゃることでしょう。
しかしながら、実際に例えば、Bさんが連れてきた買主が最良の条件で入札したとしても、Cさんの業者がそれよりも10万円上乗せする、などと始まると終わりが見えず入札に参加した買主にも失礼ですし、入札の条件がばらばら(例えば建物又は残置物撤去や確定測量の有無など)だったりすると何をもって最良の条件と言うかどうかも不明確です。
入札合意書の作成によるトラブル回避
そこで、わたしは弁護士として入札のスキームを作るだけでなく、「日時場所を特定し、その時刻その場所に最も最良の条件で入札した者を買主として売買契約を締結することを約束する」入札合意書を作成し、B、C、Dさんにそれぞれ署名押印をして頂きました。
さらに、この入札合意書には「契約不適合責任を免除すること(ただし心理的瑕疵はないことを保証すること)、建物内残置物は売主で撤去すること、戸建て宅地については確定測量と境界確認を必要とすること。」などを骨子とし、売主に仲介手数料を求める場合にはその額を入札金額から差し引いた後の額をもって最良の条件とすると定義しました。
また、最良の条件の買主と売買契約を締結しない場合には、入札価格の2割を違約金として他の共有者に支払うことも明記し、入札後にB、C、Dが売買契約が締結できるようにしました。
このような入札事案では、
①最高値を付けた入札書に契約不適合責任の免除を「建物」だけに限り「土地」は引渡しから3か月記載していたため失格となったこと、
②売主の仲介手数料なしの5000万円の入札と売主の仲介手数料ありの5150万円の入札で前者が落札者となったこと、
③落札が決まったのに売主共有者の一人がもっと高い金額で申し込む買主を見つけてきて入札の結果を受け入れなかったこと(この結果、先の入札合意書の記載のとおり入札額の違約金2割を要求することになったこと)、
などのトラブルがあったことがあります。
しかし、きちんとした入札合意書を作成しておけば、このようなトラブルにも対応できることになります。
|
|
執筆者:鈴木洋平 |
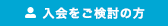
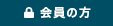
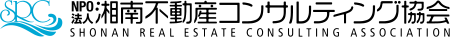




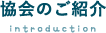






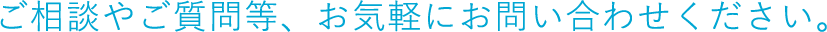
![お電話でのお問い合わせ 0466-25-5253 営業時間 10:00-17:00 [水・日曜定休]](/images/common/contact_tel.png?t=2)